いやぁーすっかり年末ですね〜。
年末といえば、忘年会、突然の人事異動、賞与の一時の興奮、クリスマスや大晦日・・・・
そして、年間ベストアルバムですね。
15枚、選びました。
独断と偏見による個人の好みが順位に出ておりますが、ひとつの思い出として収めさせていただきます。
順位や点数は、自分が音楽に求めている美しさとは少し違うけれど、長く音楽を楽しむ上で、結構価値のある整理なので、乗っかろうと思います。
ぼくが今、超絶好きなAlex Gは、一般の方の年間ベストから、「この人のおすすめなら…」と出会ったので、全然バカにできません。作品と同じく、それぞれに生の声があって、価値があると思います。
今回ぼくが重視した前提は、こんな感じです。
・来年も聴き返したい、消費されない作品。
・アルバム通して退屈しない作品。
・月曜日の憂鬱に寄り添うキャッチーさ。
・透明感(に近いものが少しでもある)。
少ない回数だけ聴いて、まるで消費するように満足するものではなく、これからも聴き返したくなる音楽を選びました。
新譜を聴き込んだ方には、そこまで斬新なラインナップでもないかもしれませんが、改めて良さを再確認していただり、「あ〜!なんか、わかる〜!」と共感いただければと思います。
それでは早速どうぞ〜。
15:Big Red Machine『How Long Do You Think It’s Gonna Last?』
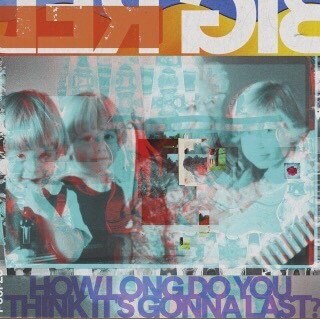
まるで大自然の中で、焚き火を眺めているように、心地良い音の粒が、ずっと流れてくれるアルバムでした。焚き火って、なんだかずっと見ていられますよね?あの時の感覚に近い…。
ザ・ナショナルのアーロン・デスナーと、ボン・イヴェールのジャスティン・ヴァーノンのバンドユニット。様々なゲストに迎えていて、フリート・フォクシーズや、テイラー・スイフトなど参加しています。アーロン・デスナーは“良い音楽を楽しんで創作する”ことをモットーに、様々なアーティストと交流しながらこの作品を創りあげたそう。確かに、このアルバムは、音楽業界の競争原理から離れた、”良いもの囲んで楽しもう”という人間本来が持つ優しい本能を、湧き起こしてくれます。
「これはいつまで続くの?」というタイトルからは、自粛期間での制約なども連想されますが、そういったフラストレーションを誰もが抱えた2021年に、そっとそばにいてくれるアルバムのひとつでした…!

14:Bruno Pernadas 『Private Reasons』
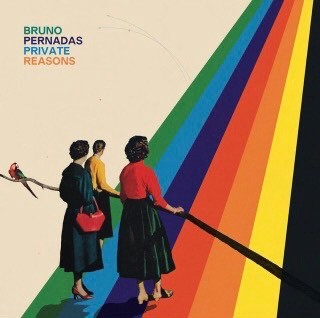
ポルトガルの音楽家、ブルーノ・ぺルナーダスの新作。気持ちの良い晴れの日や、お酒を呑んでる時に聴くと、いっそう小躍りして聴きたくなる楽しいアルバムでした。テーマは”未来的なアフロビート”だそう。踊りたくなるような民族音楽のワイルドな力強さを感じる裏で、繊細でジャジーなサウンドの気配りも楽しめました。ぼくには洒落すぎているかもしれないけれど、これからもたまに聴き返したいアルバム。US/UKの音楽とは少し異なる音楽の面白さが、わかりやすいサウンドです。「ワールドミュージックは、底知れなく広いんだなぁ」と思い知らされた作品でもあるかも。

13:Drug Store Romeos 『The world within our bedrooms』
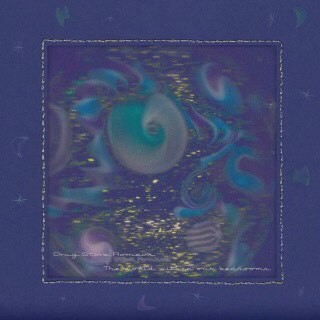
「私たちのベッドルームの中の世界」
シンプルで良い響きのタイトル。
コロナ禍であったからこそ響くタイトルでもありました。夏にリリースされたと思うんですけど、夏の夜にハマります。
このアルバムはなんだろう、夢の中を泳いでいるような心地になるんですよね。このバンドの音楽もまさにドリームポップ。けれど特徴的なのは、ロックの淡々としたビートを、幻想的な世界観に混ぜ込んでいるところ。ベースとドラムがとてもクールでミニマルで、一見単調なんだけど、飾らない魔性のリズムが彼らの持ち味です。ドラムとベースで作り込まれた流れの中を、漂うような気持ちになるので、浮遊感というよりも、“泳ぐ”といった感覚を持つのかもしれない・・。その個性的な音の流れに、サラのささやくような、愛嬌もある歌声が合わさって、このバンドならではの独特の世界観を創っています。また夏の夜に聴きたい!

12:Dry creaning『 New Long Leg』

2021年話題になったサウスロンドンのポストパンクバンドの一つ、ドライクリーニング。
淡々と囁くように歌うフローレンス・ショウのヴォーカルがやはりカッコいい…。このヴォーカルがささるかどうかで、好みかなかり分かれそう。彼女のスタイリッシュな囁きと、ミニマルだけど躍動感のあるギターの音色が、まるでツインヴォーカルのように対等に調和していて素敵でした。
そういえばドライ・クリーニングは、行きつけの音楽好きの美容師さんから教えてもらいました。SNSには沢山いらっしゃいますが、こういった音楽を好きな方に、たまたま日常で出会えるのは、このご時世、貴重ですよね笑。音楽友達が全然いないぼくにとって、珍しくネットとは違うところから出会った音楽でした。たぶん再来年くらいに改めて聴き返したとき、「うわあ、めちゃくちゃカッコいいな」と思い返せる、永くカッコいい作品。

11:betcover!!『時間』

これ、ほぼ一発録りされた音源らしいですね。
一発録りだからこそ、ローファイな仕上がりになっていて、ヤナセジロウのアーティストとしての勢いをとても感じるアルバムでした。退屈する曲が全然ない。音の重なるノイジーな演奏なときも、全然うるさくは感じない。音の使い所がわかっているなぁ…。スピード感の強弱もあって、アルバム通して非常に面白かったです。
邦楽、洋楽と分けるのはアレですけど、邦楽の根底にある歌謡曲的な要素に、いろんなカッコイイものをぶち込んで、彼なりに錬成し直した音になっていて、なんだかどことない懐かしさと、新しさが混ざっている。懐かしさと新しさが同時に味わえるアルバムでした。
収録曲のどれも良曲ですが、狐、島、pianoあたりの疾走感が個人的にカッコイイ…!
ちなみにぼくのベストトラックは島です。
今年生でライブ観れた人、羨ましいなぁ…。
来年は是非ライブを体験したい…!

10:The Weather Station 『Ignorance』

「2021年はフォークがきている」なんて盛り上がりをTwitterでみかけましたけど、きっとこのアルバムの存在は大きいでしょう。カナダ出身のタマダ・リンデマンによるバンド。少し低めで繊細な美しい歌声と、躍動感のある演奏が合わさって、よくあるフォークソングから一線を画しているようなサウンドでした。フォークにしては、結構テンポの速い曲が特にアルバムは前半多くて、疾走感があるんですよね。SSWにみせかけて、バンドサウンド重視であるのも理由だと思います。個人的にこのアルバムには、疾走感や躍動感を求めて楽しんで聴いています。例えば、2曲目のAtlanticなど、このスピード感のあるフォークがThe Weather Stationの魅力のひとつですよね。
3曲目のTriied to Tell Youでは、こちらは80年代を連想するズンズンとしたイントロのリズムがかわいいし中毒性がある。ヴァイオリンのような音色のアクセントで聴き惚れます。このアクセントはこのアルバムで一番好きなぼくにとって主役の音色。
ピッチフォークでも高評価だった作品。あえて意見を言ってみると、前作にスピード感のある曲が集中しており、後半にゆったりしている曲が固まっているのが、少しムラがあって、個人的にちょっと惜しい。もちろん人それぞれの好みですけど…!なんにせよ21年のフォークシーンを代表するアルバム…!

9:Madi Diaz 『History Of A Feeling』

アメリカのナッシュヴィルを拠点とする女性シンガーソングライター。
のびのびとして力強い彼女の歌声と、ギターのローファイな音色が、次第に盛り上がっていって、後半は少しずつ落ち着いていくアルバム構成。このアルバムは、曲順に通して聴いて、全体的な抑揚を楽しむ音楽でもありました。前半は、静かな演奏の中で、彼女の声が強調されたしっとりしたサウンドになっており、それがじわじわと盛り上がっていきます。中盤になると、いつのまにか演奏がバンドサウンドになってきます。Think Of Me〜Nevousのあたりですね。綺麗な弧を描くように、美しく盛り上がって、潔く静かに終わっていくアルバムでした。
このアルバムはSNSでふと知ったアルバムです。Twitterのタイムラインは、工夫すれば、本当に良質な音楽に出会える場所ですね。今年もフォロワーさん方に感謝です。

8:Cassandra Jenkins 『An Overview on Phenomenal Nature』
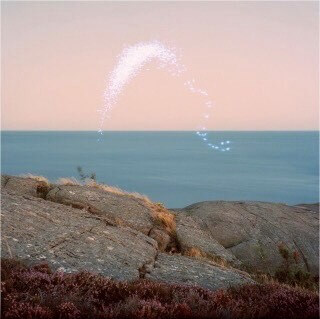
ニューヨークのシンガーソングライター、カサンドラ・ジェンキンスによる、バンドメイトであった友人の”死”をきっかけに作られた2ndアルバム。このジャケットのアートワークには、そういった鎮魂歌のような意味合いも込められているように思えます。ぼくとしては「シンプルに、MichelangeloとHard driveの2曲がぶっちぎりで、めちゃくちゃ良いなあ・・」というのが、このアルバムを聴いて、まず思った率直で稚拙な感想です。
運転している時に Michelangelo を聴いていたら、ふと泣きそうになりましたもん。
このアルバムは、アンビエント・フォークと取り上げられています。正直いってしまうと、最初、上記2曲以外の印象が薄いと思ってまいました。けれど、確かに、この2曲のアンセムを軸に、全体を包括する落ち着いた曲を、一つのまとまりのアンビエントの音色として解釈すると、彼女がこのアルバムで表現したかったイメージが伝わってくる気がしました。あまりポップな部分は求めず、ただひたすら、音色をじっくりと耳に染み込ませるように、これからも聴きたいと思います。

7:Tempalay 『 ゴーストアルバム』

最近、清々しい透明感のあるサイケデリックな音が好きなんですけど、まさにテンパレイはそんな音を奏でてくれる、いそうでいない貴重な日本のバンド。このアルバムの”良い塩梅の透明感のあるサイケ”がとっても気に入っています。薄すぎず、濃すぎない、けれど、妙に耳に残って、聴き返したくなる…。
2曲目の『GOHST WORLD』は、サビにかけて、すうっと身体をすり抜けるような、まさに幽霊を連想する音色で、森道市場でも生でライブをみれましたけど、ふと鳥肌が立ってしまう緩急が魅力の名曲でありました。
6曲目の『春山淡治にして笑うが如く』のような和洋折衷なサウンドも個人的に好みで、それにAAAMYYYとの美しいツインボーカルのコーラスも合わさって、リスナーを飽きさせない音の移ろいが味わえる。
そして今回、このゴーストアルバム は、アルバム構成がとてもバランスよく、くどくもなく、退屈せずに、何度も周回して楽しめるアルバムでした。最後は『大東京万博』で、流麗に幕を閉じます。
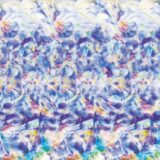
6:パソコン音楽クラブ 『See-Voice』
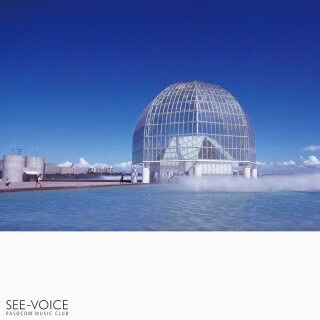
まず、知らなくてもジャケ買いしたくなるほどアートワークが好みです。素敵なジャケットです。“水”をテーマに歌詞や世界観が統一されており、内省的で透明感のある落ち着いた作品となっています。このブログのテーマカラーをみていだければわかると思いますが、ぼくは水色が大好きなので、なんかもう、そういうテーマってだけで既にかなりささります。
パソコン音楽クラブとしては、前作までから大きく作風を変えた今作。やはり自粛期間の影響もあったようで、ダンスミュージックよりも精神的な内面に関わってくる音楽に自ずとなっていったそうです。いや〜暗いぼくの個人的な好みに仕上がってますね~。
レトロ感が、ぼくが勝手にこのアルバムで楽しんでいるキーワードで、シンセだけど、彼らのこだわる機材や音の表現方法が、懐かしさを覚えるサウンドを生み出している。もちろん、決して古臭くはない。また、ゲストヴォーカルの弓木英利乃やunmo、川辺素(ミツメ)の歌声も少し懐かしい。ちょっと昔のゲーム音楽や古めのアニメのOPも連想します。彼らの中で重宝されているこのレトロ感は、自分の好みに刺さっている。ぼくの年齢が彼らと近いので、ぼくらの世代なりのレトロなのかもしれないです。
呑んだ後に歩きたくなって、ほろ酔いのまま2時間外を歩いた時に、今作を初めてしっかりと聴いたのが馴れ初め。『遠くまで/Far』を聴きながら長時間歩いた、あの時の心地よさはなかなか忘れられない。
インストも多いので、BGM的な聴き流す心地よさもあったりする。超個人的な体験ですが、ほろ酔いで散歩しながら聴くのがおすすめのアルバムです。是非お試しください。
このアルバムで、いままでのダンスミュージックの殻をむいて、また新たな音楽性に向き合い始めたパソコン音楽クラブに拍手です。

5:Ruby Haunt 『Watching the Grass Grow』

LAを拠点に活動するデュオのプロジェクト。
この言葉は迂闊に言いたくないですけど
チルです。これぞチル。
もはやこの言葉は、簡単に消費されすぎて、何でもかんでもチルと言われていますが、ぼくが心の底からチルだと思う作品。そして静かだけど、エモーショナルでもあります。仕事で疲れ果てた帰り道とか、心が落ち着かない日曜日の夜とか、カフェインレスコーヒーで身体を温めながら、間接照明をつけてこの音楽を聴くと最高です…
いや〜染みます。
眠くなるので、この音楽は運転中には聴けないみたいなこともありましたけど、無性にこれしか聴きたくない!ってときがしばしばありました。音楽で眠くなるということは、退屈か安心するかの2種類だと思いますが、彼らの音楽からくる眠気は、退屈からくるものではなく、安心や落ち着きからです。シンプルな音楽に聴こえるけど、ミニマルな構成の中に、エモーショナルなメロディ、かすかにドリーミーなサウンドが混じり合ってRuby Hauntならではの音の境地に繋がっております。
彼らのアルバムは大体30分代でコンパクト。個人的に、弱った心で落ち着きたい時にはぴったりの長さです。そして毎回ジャケットのアートワークが彼ららしさ満載で、ぼくが好きな風景にいつも似ている。ぼくはキャンプとかもたまにするので、来年もたまに1人で早起きして、早朝に彼らの音楽をこっそり聴きながらコーヒーをのみたいなぁ…

4:Claud 『 Super Monster』

NY拠点のシンガーソングライターのクロード。2021年も女性SSWの新譜はそれもう良い作品がたくさんありましたけど、個人的な意見としては、クロードのこのアルバムが最もハマりました…!
カッコつけたりしすぎずにポップ、だけどジャケットからは想像つかないくらい、切ないメロディが流れて、センセーショナルで繊細。ベッドルームポップの良いところが詰まってます。
彼女自身のファッションやヘアースタイルとも、かなり異なった印象を持つ音楽ですよね。彼女自身、幼少期に両親が離婚したり、ノンバイナリーであったりと、若くても何か思うところが色々あり、こういう音楽性に結び付いたのだろうか?と憶測してしまう。「音楽と慰め・癒し切り離したい」って意見は結構見かけますけど、ぼくはそうは思わない。ぼくはどうしてもこういう切ないシンプルなメロディが好きです。正直、このアルバムのメロディと歌声に素直に癒やされている。
作品を通して、透き通った彼女の歌声が残響するようにエフェクトがかかっています。このヴォーカルの微かな残響も、めちゃ好きなところです。
曲の構成は結構シンプルで淡々としてるけれど、キャッチーで聴きやすく、アルバムとして骨組みがしっかりしています。10〜11才の頃から曲を作ったりしていたそうで。嗚呼、自分より若い人がどんどん世界で活躍していくなぁと少し寂しくなりながらも、その才能と今後の活躍に期待です…!

3:Another Michael 『New Music and Big Pop』
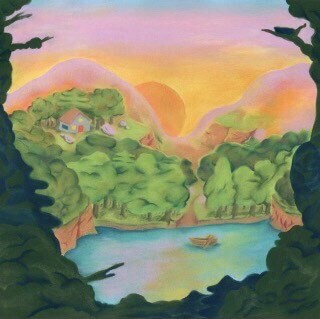
名古屋の大須レコード屋、ファイルアンダーさんで、確か、スフィアン・スティーブンスを手にとって眺めていたら、気さくな店主がBGMをこのアナザーマイケルに切り替えてくれた。ビビッときたので、どんなバンドか教えてもらったのが、きっかけでした。自粛期間もあって、レコード屋に久しぶりに行けた時の良い思い出です。フィラデルフィアのトリオバンドで、ジャンル的にはフォーク・ロック。タイトルにもある通り”ポップ”が強調されていて、アルバムを通して、非常に聴きやすいメロディが楽しめます。難解さの欠片もない、まさにポップ。
そしてヴォーカルのMichael Dohertyの中性的で繊細なハスキーヴォイスが凄まじい…!ただ、高いだけではなく、心を揺さぶる掠れと抑揚を持った、かなり貴重な声質をしていると思います。
このライブ映像がカッコいいので、是非どうぞ!アー写は少し変わった感じなので、このライブ映像は彼らのカッコ良さがビシビシ伝わります。
いや〜、カッコいいですね〜っ
デビュー作とは思えない洗練された歌声と、アルバムの良曲の多さに打ちのめされました…!ファイルアンダーさんにも感謝です。

2:踊ってばかりの国 『Moana』

めちゃんこハマりました、このアルバム。
サイケデリックなんですけど、ただ幻覚を想起させるようなサウンドってだけではなく、狂気が昇華されて、別のものに生まれ変わってていく美しさを、終始感じさせてくるアルバムでした。例えば、2曲目のNotoriousはまさにそんなイメージ。
今回の曲の多くは沖縄の自然の中で書かれたようです。自粛生活の背景もあり、今回のアルバムでは、音楽の音だけで、どれだけ自然をみせられるか、という試みがあったようです。そういった自然と音楽を結びつけるフォークに近いような意図が、特にぼくの好みに近い作品になった背景かもしれません。(今回、音楽技法的には、ジャズのテイストを特に意識していったようですが)。実際ぼくは、森道市場で海岸沿いのステージで彼らのライブを観れました。なかでもLemriaは本当に砂浜や潮風とハマっていたなぁ。この曲はぼくのベストトラックです。
アルバムと同じく、狂気と美しさの入り混じる素晴らしいライブでした。下津さんのニコニコ笑顔が、ある種鬼気迫っていましたね笑 ぼくにとっては、本当に久しぶりの屋外ライブで、バチっと決めてくれました。伸び伸びとした歌声が、空と海を突き抜けて、風と混ざって響き渡っておりました。
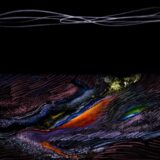
1:SPIRIT OF THE BEEHIVE 『ENTERTAINMENT, DEATH』
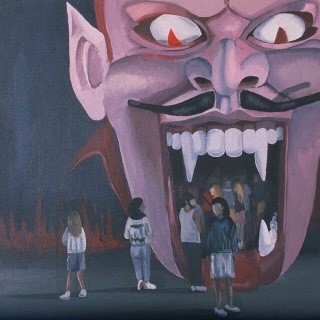
音楽本来の”繰り返して、何度も楽しめる”という魅力を体現した傑作。
ぼくのベストアルバム。
フィラデルフィア出身のオルタナティブロックバンド、 SPIRIT OF THE BEEHIVE の4thアルバムで、初の完全なセルフレコーディング作品。じわじわ~とハマった。このアルバムの魅力は、聴き終わって日常に戻った頃、むずむずと聴き返したくなるところです。
音の中毒性が凄まじい。
さらに、金曜日に踊りたくなるような魅力を持ちながら、月曜日に布団にくるまって聴いていたいような、二面性を備えてるんですよね。アルバムを通して、ジェット機のような轟音がなったり、胸がぎゅうっと締め付けられるような切ないメロディが流れたり、儚いドリーミーなサウンドに包まれたり…。急転する曲進行と、たまにだけ訪れるドリーミーなサウンドの緩急が、このアルバムの持ち味。意外とドリームポップが好きな人に、推したいアルバムです…!
中毒性をテーマに考えると、アルバムを通して飽きさせないという魅力もあります。このアルバムでは、ビデオテープの巻き戻しみたいな音がたまに使用されているんですけど、よくあるようなアルバム構成の流れをぶった切って、「はい!やり直し!」って感じで、巻き戻して何度も曲をやり直しているようなトリッキーな進行になってます。この手法のお陰で、予測できない新鮮さと飽きにくいサウンドなんですよね〜っ
そもそもの話ですが、ぼくは、「聴きかえす、何度も聴きたくなる」ということころに”音楽”の特別な魅力をかんじているんですよね。世の中にはあらゆるコンテンツがありますけど、映画や本、ドラマ、アニメなど、どんなに傑作でも音楽みたいにここまで日常から繰り返して楽しんだりしない。(まぁ単に自分が、音楽が特に好きなだけなのかもしれないですけど…)どちらにせよ、反復して楽しめるところに価値を見出してます。『ENTERTAINMENT, DEATH』 は、その詰め込まれたアイデアから、日常で何度も繰り返して楽しめるという音楽の本来の魅力が詰まっている作品でした…!

この作品については、個別で気持ち悪いほど書いておりますので、良ければどうぞ。
いかがでしたでしょうか?
すでにこの多くの作品を聴き込んでいる方も多いかもしれません。このブログを読んで「あ〜!わかる〜!」と良さを再認識したり、興味を持ったアルバムがあれば、聴いてもらえれば本望です。
自粛期間の影響かあってか、内省的な作品が多かった印象の2021年。でも、きっと世界が本調子でも、結局自分は内省的な作品を聴き漁るでしょう…そんな気がする。
いやー沢山の音楽作品、
つらかった2021年をありがとう・・・。
今年大切に思った音楽を、エンターテインメントの消費として、終わらせたくない。
大切に聴き返していきたいですね。
.png)




最近のコメント